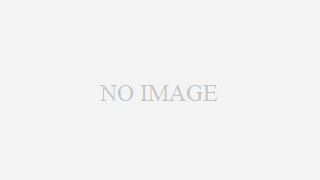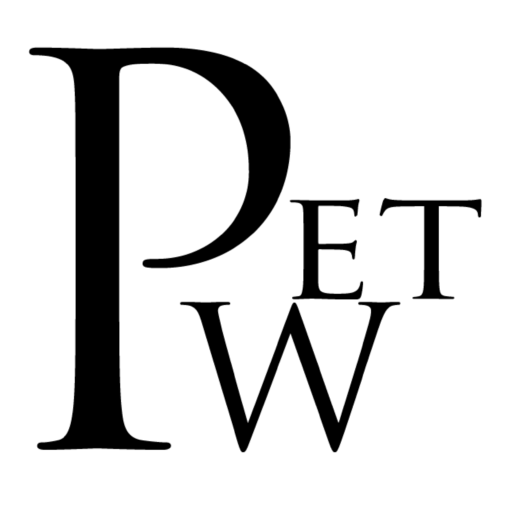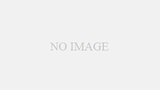はじめに
月に一度くらい、SNSでこんな人物を見かけませんか?
「まぁ、普通の飼育者には理解できない話だろうが」
「この分野では常識です」
――などと、文章の末尾に優越的な一言を添えるタイプの人です。
こうした発信は、自分が他者よりも知識的に上にいると印象づけたい意図が透けて見えます。こうした人物は、どの界隈にも一定数存在しますが、爬虫類飼育の世界でも例外ではありません。経済心理学を学んでいた友人の話によれば、こうした態度は「社会との接点が希薄になっている人間が取りがち」とされる傾向があるそうです。
今回は、このような人物の特徴や背景、発言内容を信じるべきか否かを考察していきます。
承認欲求のゆがみ
こうした発言者の多くは「承認欲求の欠如」ではなく、承認欲求の歪んだ表現と見るのが適切です。
「他人よりも知識がある自分を認めてほしい」「評価されたい」という欲求が、過剰なマウントや排他的発言につながっているのです。
このような人は、断片的かつ偏った情報を過剰に信じ込み、それ以外の情報を拒絶する傾向にあります。自分の主張を肯定する情報だけを集め、否定する情報には目を向けません。これは自己の優越感を維持するための心理的防衛機制の一種です。
医療・福祉など人間行動を扱う学問領域では、こうした行動を「社会的欲求の不安定」や「承認欲求形成期の混乱」と呼ぶこともあります。これらの場合、「自己実現欲求」が満たされていないという見方もできます。
学歴コンプレックスと劣等感
「詳しくないと思われたくない」「学歴がないとバカにされたくない」という劣等感も、このような態度の根底にある場合があります。
現代では「Fラン大学」「〇〇大学は大学じゃない」といった偏見的なコンテンツが流行し、学歴コンプレックスが強化される風潮も背景にあるでしょう。
本来、学びとは他者との比較ではなく、自分の中での知の積み重ねであるはずですが、SNSでは「相対的な知識勝負」のような環境に陥りがちです。
「半可通(はんかつう)」の危険性
表面的な知識や断片的な事実だけを信じて自信過剰になる状態は、「半可通」と呼ばれます。
大学や専門機関で学ぶ際には、知識の限界や多様な学説、例外の存在を自然と学びます。しかし、独学やSNS情報だけで学んだ場合、それらが欠落し、極端で断定的な態度になりやすいのです。
情報は常に更新されるものです。飼育や生理学の分野でも、かつての常識が今では否定されている例も少なくありません。そうした変化に柔軟に対応することが、真の知識保持者に求められます。
「中卒」扱いされる理由とは
SNS上でこのような人が「中卒では?」と揶揄されることがありますが、それは彼らの発言に以下のような特徴が見られるからです:
- 異なる立場や意見との比較ができない
- 出典や根拠の提示を拒否する
- 他者に説明する能力が欠如している
ただし、これは必ずしも実際の最終学歴とは関係ありません。精神的未成熟や自己認知の不安定さが根本にあることも多いのです。
なお、知識を他者に伝える際には「相手が理解できるように説明する努力」が基本です。専門用語を乱発してわかりにくくなるよりも、丁寧で親切な言い換えができる人ほど、本当の意味で知識を深めている証です。
ダニング=クルーガー効果の影響
このような傾向の背後にある現象として、ダニング=クルーガー効果があります。
- 能力の低い人ほど、自分の未熟さに気づけない
- 他者の能力を過小評価し、自分の知識を過信する
こうした人は、Twitter(現X)でも以下のような表現を好んで使います:
- 「普通の人には理解できないと思うが・・・」
- 「最低限の知識を身につけてから発言してください。」
- 「この業界では常識ですよ。」
しかし、そうした“常識”がどこまで確かな情報に基づいているのかは、慎重に見極める必要があります。
当サイトが気を付けている事
わたしのサイトも例外ではありません。他者に情報を発信し毎日数百人に閲覧されている以上、情報に責任を持ち常に最新の情報を取り入れる為に多くの記事で「2025年版」などの年数を書きます。最新の情報が得れていない場合や、更新がない場合は2024年版と書かれていますが、前年度の新たな思考や情報を取得し整理することができれば加筆、訂正し2025年と書き換えています。
さいごに
そのような人物がすべて間違った情報を発信しているわけではありません。
問題なのは、「少数の特殊なケース」を「一般常識」と錯覚して語ることです。たまたま経験した稀な出来事が、自分の中で絶対的な真実になってしまうのです。
情報に触れる側としては、出典、事例数、学説の裏付けなどを冷静に見極める態度が求められます。
SNSは便利な情報源であると同時に、誤情報や偏見が交錯する場でもあります。健全な知識の共有と議論が行えるよう、私たち一人ひとりがそのリテラシーを意識していきましょう。
友人曰く、このような人たちは多くの場合、大学新1年生である可能性が高いとのことでした。確かに新たな環境で精神的欲求が不安定である一方、新たな知識が多く入ってくることで、大学入学前に事前に学んだ情報の整合性を指摘されれば、そのような人になるのも想像できますね。