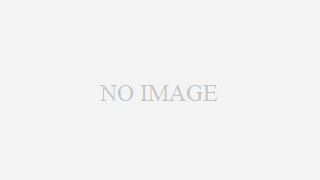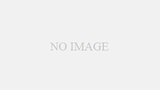【2024年版】グリーンパイソン飼育のすべて!初心者から上級者まで必見のコンテンツ
はじめに
日本での一般呼称は「グリーンパイソン」、正式和名はグリーンツリーパイソン(学術名:Morelia viridis)です。ニューギニアとオーストラリアの北部に生息している美しい爬虫類です。鮮やかな緑色と独特の形状が特徴で、爬虫類愛好家に非常に人気があります。生まれた時に黄色の体を持ち、成長と共に緑になったり、産地によっては青が出てきます(アルー産)。また、生まれた時に体が赤い個体をレッドと呼び、そのレッドは成長しても体に黄色を多く残すことができます。専門的な飼育方法について説明します。

緑の帯が闇夜を照らす、 煌めく星々に紛れる美しき者。 空を舞う神秘の魔術師。 熱帯雨林の奥深く、 織りなす緑のカーテンの中で囁く。 静かなる風と共に揺れる葉の音色、 まるで、語りかけるかのようなその姿。 神秘的な瞳に秘められた知恵、 遥か昔より継がれる自然の掟。 草木と共に生きる者、 グリーンパイソン、その姿が示す。 優雅に空中を舞う緑のリボン、 輝く瞬間を求めて進む。 重なり合う運命の音楽に耳を傾け、 緑の舞者は、今宵も輝きを放つ。 魅惑の存在、 どこにいても輝く。 夢の中で囁くその詩、 まるで、闇夜を照らす緑の煌めき。
グリーンパイソンの飼育方法の要点
- 飼育スペース:十分な大きさの高さのあるゲージ、枝や棚の設置、適切な換気
- 温度管理:昼夜の温度差を作る、天井型ヒーター等で調節
- 湿度管理:50〜70%の湿度を維持、ミストや水槽を利用
- 床材:吸湿性のある床材を選び、定期的に交換
- エサ:小型哺乳類を与え、若い個体は週1回、成体は2週間に1回のペース
- 水:常に清潔な水を提供し、毎日取り替えが好ましい
- 病気:お迎え時ワイルド個体の場合、感染症または寄生虫を保持してる可能性が非常に高い。
グリーンパイソンの特徴(生息地と環境)
グリーンパイソンは、オーストラリア、インドネシア、パプアニューギニアなど、太平洋地域の熱帯雨林に生息している大型のヘビです。彼らは主に樹上性の行動傾向が強く、樹木の枝や葉の上で生活することが多いです。そのため、環境が整った熱帯雨林では豊富な樹木や植物が生育し、多様な鳥類や小型哺乳類が生息しており、十分な食物が確保されています。また、樹上での生活に適応した特化した体の構造と、環境に溶け込む独特のカモフラージュ能力を持っています。
成体は一般的に全長150cmから180cmほどで、緑色の体に白や黄色、青などの鮮やかな模様が特徴的です。若い個体は黄色から赤褐色で、成長するにつれて緑色に変化します。
グリーンパイソンは、夜行性であり、主に夜間に活動し、昼間は樹上で休むことが多いです。そのため、尾の先にある「尾緒」を使って枝に巻き付き、体をぶら下げてバランスを取ります。また、熱感受性ピット(熱受容器官)を持っており、暗闇の中でも獲物の体温を感知して捕らえることができます。
樹上での行動に適した体をしており、歯も特徴的で鳥の羽を貫通できるように鋭くなっています。また、オスメス共に背骨が浮き出ている程度が正常であり食欲旺盛ですが、樹上生活が主なこともあり気性は荒く動きは素早いです。パイソンと名はついていますが筋力は対して強くなく、中型種と言う意味でついています。
歯は鳥類の捕食に適し、羽を貫通することに特化した長い歯を持っています。
ケージの選び方
グリーンツリーパイソンは長年の飼育知識から、縦の行動より横の行動を好むことが観測されています。特に何段にした方が良いとはありませんが、最上段以外は、床から最上段に上がる為の段差(棒)と考えることが良いとされています。つまり、生体の大きさに合わせて段差を増やす必要があり、フルアダルトになると、最上段の棒だけで十分であることが多いです。グリーンツリーパイソンは成長に合わせたケージの拡大は不要であり、成長に合わせた上り木の準備が重要です。
また、ヒートトップがほぼ必須であり、天井部は高温耐性のあるメッシュタイプが最適です。
指標① 横に大きく自由に移動できる環境
世界的な基準であり最もストレスがないとされる環境:
グラステリア6045で十分ですが、装飾をする場合はそのオブジェクトで範囲が狭まる為9045が適しています。また、飼育部屋の基本温度が高く(30℃など)、ホット/クールスポットが区別できない場合は60より、より横に長い9045がお勧めです。
指標② 高度なエアコン管理をした、上下できる環境
高さを重視したホット/クールスポットを縦に作る環境:
現在はハイタイプは3060しかありません。過去には日本では主流ではありましたが、ストレス解消を重視した際には横の広さが重要視されるため、指標①に変わっていきました。サーモスタットを上部に設置し、下の段が必ずクールスポットとなるように、季節ごとに正しく設定する必要があります。
指標①が圧倒的おすすめ
多くの検知や観察から言えるように、最上部での横方向への移動を好みます。特に床と近いからダメと言うわけではないですが、成長すると、より一層捕食時に下を向くことが多いので下に垂れたときに床に当たらないほどの十分な高さが要求されますが、現状、生体の平均体長から高さは60㎝ケージの物あれば十分と言えます。また最大の重要ポイントですが、指標①の場合、幼体からフルアダルトまでそのケージの利用ができるメリットがとても大きいです。またエアコン管理よりホットスポットの形成が重要な種類とされています。
温度と湿度の管理
温度管理
- 昼間の温度は27℃~30℃
- 夜間温度は24℃~26
または
- ホットスポット32~33℃前後
- クールスポット 最低20℃
昼夜の温度より、ホットスポットの温度を重視します、クールスポットは最低温度を考慮しなくても自ら好きな温度に移動する為考慮の必要はありません。グリーンツリーパイソンにとっては最低温度20℃を下回らない事が重要であり、ホットスポットを形成するヒートトップが故障していないことをよく観察する必要があります。ヒートトップを設置して、最上段の横棒が、ヒート下32~33であればエアコン管理は不要です。
湿度管理
特段湿度を気にする必要はありません。蛇の中でも比較的水分摂取が積極的な種類でもあります。
- 湿度常時50%~70%
- 脱皮時のみ一時的に90%など
グリーンツリーパイソンは高湿度に弱く呼吸器疾患を患います。また湿度変化に敏感であり湿度変化は極力起きない一貫性のあるケージが重要であり、霧吹きで調整より、水コケボックスを設置して、日頃から湿度を一定化させることが重要です。脱皮時においての90%は霧吹きでの結果であり、わざわざ90%を一定化させるのは危険とされています。
温湿度計の使用
通常、天井型のヒーターが右側に設置している場合、温湿度計は右側でなおかつ横木と並べるように設置します。ヒーターの真下ではなく、手前か奥にずらしたところ置くことが良いです。理由としては、ヒートスポット周囲の温度と湿度が重要で、尚且つ、グリーンパイソンが好む、高い段の横木の温度と湿度が最適な方が良いからです。他の場所に設置したら、飼育部屋の温度を測るだけになってしまいます。対してサーモススタットで天井型のヒーターを管理する場合、ヒーターがある逆側にサーモスタットを設置するのが普通だそうです。
部屋自体をエアコン管理する方法があります。これらはケージの上部の面積が小さくヒーターを設置できない場合に使用されますが、あまり良い環境ではないと言われています。ホットスポットとクールスポットをケージ内に作り温度差を作る事が重要です。
ヒートトップかバスキングライトを使用
海外例としてヒートトップではなく、多くの爬虫類で使用されるバスキングライトをケージ上部から照射する方法もあります。ただし、バスキングライトは視光性紫外線ライトと非視光性紫外線ライトがあります。視光性を使う場合は夜間様に非視光性も準備する必要があります。影を形成するひつようがあるなど少しレベルの高い飼育方法です。日本においては販売されているケージサイズが小さいです。無難にヒートトップをお勧めします。
床材の選び方
床に降りることは限られます、その点において床材は考慮しなくてもよいです。ただし、産地により脱皮時は床に降り脱皮柄を剥ごうとする行動を行う個体もいます。その為、糞尿の清掃のしやすさや衛生面が重要です。
スネークチップ:細かい蛇用の木くず、糞尿のみをピンポイント捨てることができ、水分吸収による腐食も少ない。
乾燥コケ:水で溶かすホームセンターなどの園芸で販売されている物です。湿度管理には最適ですが菌の増殖を抑えるためにこまめな交換が必要です。また底面の面積が狭い場合は良いですが、広い場合はかなりの量が必要です。
ケージ内のインテリア
テラリウムを行う場合、より陰性の観葉植物をポットのままケージ内に置いたり、天井部に造花のツル状の物を付けたりする人が多いようです。ただし、それらを設置した際は、個体がそれらに巻き付いた際に、取れない、倒れないようによく固定しましょう。
海外例ではありますが、完全なテラリウムを行う場合と、まったく装飾しないという極端に分かれます。
また、横木は2段にして下に降りの際に上に容易に戻れるようにしましょう。ケージの奥側上部に1本、ケージの手前側中断部に1本が理想です。使用する横木はグラステラリウムの場合、横木を吊り下げるものが一つ付属されています。(本来はバスキングライトをつけるものです)それらを使う事もできますが、100円均一の突っ張り棒がお勧めです。これらは、2個並べることで成体の成長に合わせてサイズを変えることができるからです。
その他必要品
餌を与える際は、竹製のピンセットを使用しましょう。ワイルド個体のグリーンパイソンは寄生虫や感染症を保持している可能性が高いとされています。生体1匹ずつに専用のピンセットを使用することがお勧めです。鉄製のピンセットなどは腐食性がある為、こまめな道具の消毒が必要なグリーンツリーパイソンには不向きです。
また、ケージの正面以外を黒くする加工を施す場合が爬虫類飼育では多くあります。水槽用のバックパネル、またはバックシートを使用してケージ手前、天井、床以外を暗くすることができます。ただし、これは好みの問題で、合ってもなくてもそれほど生体には影響は及びません。周りが明るすぎる場合はとても有効だと思います。車用品の塗装スプレーで黒などで塗装すると容易に暗くでき剥がすときもシンナースプレーをかければ容易に元に戻せますが使用上の注意をよく読み使用しましょう。
飼育の裏技
脱皮兆候を見つけてからの霧吹きの代わりとして熱帯魚飼育用のエアレーションとエアーストーンのセットをケージ内の水につけて起動させることでエアーストーンの泡の効果により、ケージ内の湿度をあげることができます。総額1000円で施工することができるためお勧めです。水入れにストーンを入れる際はエアーストーンが底面に当たらないようにしましょう。底面に当たっていたらケージ全体が激しく振動してしまう可能性があります。
照明の必要性
長年議論されていた項目であり、動物福祉を考慮したUVAの使用は推奨されています。ただ必須というわけではなく、UVAを設置する場合はその光から隠れることができる場所を作るか、UVAの出力自体を低出力LEDなどの弱いものにしましょう。
グリーンパイソンの食事と栄養
餌は他蛇同様、マウスをあげる事が一般的です。野生界での生態を模し、鳥を給餌することは可能ですが、栄養価ではマウスの方がとても優秀である為、マウスをあげます。以下で詳しく解説します。
食事の頻度と量
一般的にグリーンパイソンには幼体であっても成体であっても週に1回胴体と同じ大きさのマウスを給餌します。拒食をします。拒食スイッチが入ると1年間は餌を食べなくてもほぼ痩せていきません。
餌の回数は増やさない
樹上性パイソン特有、とどまっている場所と胴体との設置点に圧迫点ができる、そこが胃や腸の動きを阻害して糞ず詰まりを起こしやすいとされており、餌頻度はなんどもあげないがベストです。
餌の種類と与え方
餌は栄養バランスの取れたハツカネズミを使用することが好ましいです。一度鳥類を与えてしまうと、鳥しか食べなくなることで有名です。また、ラットでも代用が可能ですが、なるべく消化効率が良く、免疫力を高める栄養が多いハツカネズミを主に与えた方が良いとされます。鳥類は栄養素が限られることから推奨されません。
栄養バランスの管理
ほんの少しやせており、少し皮がある程度が適切な状態と言えます。樹上を好む蛇は骨格が浮き出ている程度の体重を維持している場合が多いです。パイソン系統は食べて消化が済んだらすぐ排泄するわけではなく、便がある程度溜まってから一気に排泄します。排泄を待たなくてもいいですが、糞つまりを見極めるのは大切です。排泄頻度は少しは記憶しておきましょう。2週間に1度排泄しているのであれば、適切なサイズのマウスを給餌できていると考えるのが良いと思います。
脱皮の準備工程、脱皮が完了するまでは食べません。給餌をしてみて食べないなと思ったら1週間以上時間を空けてあげる事をお勧めします。
グリーンパイソンの水分管理
大きな水入れを用意してください。小さいと個体がどこに水があるのか分からず、水を飲まずに死ぬ例もあります。容易に見つけることができるサイズの水飲み場を用意しましょう。
水の交換は毎日が推奨されます。
水のみに関する重要な注意点
グリーンツリーパイソンは霧吹きをしないと水を飲まない傾向を持つ個体が一定数います。これは熱帯地域の爬虫類の特徴で見られ、雨が降るとその水を飲もうとして行動を行います。水交換をしたタイミングで霧吹きを十分に行ったり、3~4日に1回、適度に霧吹きを行うとよいとされています。
グリーンパイソンの飼育下での繁殖
海外ではとても人気である種類である事から、繫殖方法に関連する情報は比較的多いです。また、グリーンパイソンの繁殖は容易ですが、卵から出てきた子供の管理が少し難しいと言われています。
繁殖に必要な条件
グリーンパイソンは成長に応じて体の色が黄色から緑に変化していきます。緑に変化した時点で成体になったと判断して問題ないと言われています。ただし、一部のバンカなどの産地においては、赤から黄色、緑に変化して、緑になっても黄色が残っている特徴があります。体のほとんどが緑になったら繁殖は可能と考えた方が確実です。
また、オスは生殖器の管に溜まったプラグと言われる、へその緒のようなものを出すことがあります。このプラグが出たら、性成熟したと考えられるのが一般的でこのプラグが出てさえいれば、体の色の進行は関係なく繁殖行動ができます。ただし、メスは性成熟にはオスと比べて約1.5倍以上の時間と体重を必要とする為、注意が必要です。具体的な数字とすれば、オスは2歳、メスは3歳を超えてから繁殖が行うことができるとされていますが、餌の頻度や環境により性成熟が遅れる可能性があります。
繁殖の方法
広いケージに2匹を入れておくだけで繁殖は可能です。総排泄腔と総排泄腔をすり合わせて手を結んでいるようにしていればそれは繁殖行動をしていると言えます。推奨されるやり方は、ケージ内に園芸用の鉢をつるして置きその中に乾燥苔を引いておくことで、その中に産み落としその卵をメスが守ります。メスを慎重にのけて設置した鉢植えをどけます。そして卵を採取します。他の蛇の場合はメスにすぐ給餌できるように卵の匂いをのける必要があると考えて体を洗うことがありますが、グリーンパイソンは気性が荒い為難しいとされています。
卵の管理方法
産卵した後そのままにしておいてもメスが温めて孵化しますが、メスへの負担が大きいく孵化するまでの約2か月間、餌を食べなくなるため。卵を採取してインキュベーターで管理することが一般的です。
インキュベーターでは、温度28度~31度を維持させて湿度を90%~99%を維持する必要があります。バーミキュライトと言われる爬虫類専用の卵用床材の上においてインキュベーターに入れます。注意が必要なのは、多くの蛇でもそうですが、グリーンパイソンは卵の向きを変えてはいけません。その為卵の回転させる機能があるインキュベーターの場合は機能をOFFにしましょう。また、卵を採取する時は卵を回転させないようにそのまま卵をバーミキュライトの上に置きましょう。卵が転がらないようにバーミキュライトの卵を置くところをあらかじめへこましておく必要があります。
また、卵の設置が完了したら、部屋を暗くして卵にライトを当てて卵内に血管が少しでもあれば、それは有精卵です。なければ無精卵かダミーである為、排除して、有精卵のみインキュベーターに入れましょう。無精卵、またはダミーの卵の場合、インキュベーター内で腐り同じ入れ物に入れている有精卵が腐る可能性があります。
孵化後
孵化後はすぐに取り出して、湿度が80%温度が28度前後の狭いケージに個別に入れましょう、そのケージの中には木登りできるために横木を入れておく必要があります。床に乾燥苔と0.5㎝程の水を引くことが良いとされています。
ファーストシェッド(初脱皮)が済むまでその小さなケージに入れて給餌はしません。ファーストシェッド後、成体のケージと同じような環境で飼育でき、給餌させることができます。
グリーンパイソンの健康管理
野生個体(ワイルド)は、感染症または、ほとんどの場合、寄生虫に侵されています。その為、輸入した店舗は、販売まで2週間程度の待機期間を作り。排便を動物病院に持ち込み検査を行います。寄生虫ほ保持した状態で購入した場合、排便内に虫がおり、知識がなくても容易に判断できます。一般的な飼育者でも寄生虫は容易判断できることから、これらの検査は知る限りすべてのショップが行っています。ただし、薬の効果が十分に発揮できず、保持した状態で販売されることがある為、信頼があるショップで購入することをお勧めします。 グリーンパイソンは世界中で人気な為、繁殖個体(CB)も多く供給されています。
5.1 病気の予防と対処法
病気の予防方法
爬虫類は感染症が流行る事があります。個別のピンセットを準備する必要があり。特にワイルド個体のグリーンパイソンは寄生虫、感染症を持っている可能性が非常に高い為注意が必要です。
病気の症状と対処法
寄生虫や感染症の疑いがある場合はすぐに病院に行きましょう。他の個体を触る時は十分に手を消毒する必要があります。
グリーンパイソンはよく脱皮不全に起こります。これは天井型のヒーター、エアコン管理をしている弊害です。ケージ内の湿度を維持していれば起こりにくいですが、脱皮不全の特徴として、体から脱皮側が浮いていても何週間も脱皮しない事があります。一部分のみが剥がれており1週間脱皮しない場合は人間が手で取ってあげましょう。握っているだけで様に剥ぐことができますが、気性が荒いので注意が必要です。
また脱皮がある程度できていてもしっぽに脱皮の皮が残っているときはかなり危険です。尻尾が腐って落ちる可能性があります。これはグリーンパイソンの尻尾が樹上行動に特化しており尻尾が長い事が原因です。噛まれる覚悟でするより、先に霧吹きを一日2回以上行いそれでもだめなら、霧吹きを事前にして、爬虫類用の安全手袋をつけて皮を剥いであげましょう。
これらの脱皮不全を予防するためには、常にケージ内の湿度を高く維持するための設備を整えて、目が白濁したり体が白くなるなど、脱皮の兆候が現れたら脱皮するまで細かく霧吹きをすることが大切です。
獣医師との協力
多くの場合爬虫類を診断できる獣医は少ないです。購入店で事前に、診断できるお店を探しましょう。基本的に爬虫類を見ることのできる医者は爬虫類の種類に関係なく見てくれます。
定期的な健康診断
特段変わったところがなければ注意することはありませんが、以下の事がある場合は注意しましょう。
- よだれを常に出している:マウスロット
- 木に登らない:ストレスまたは感染症による衰退
- 木からよく落ちる:環境不適合、横木を太くしてあげましょう。
- 排泄物の中に虫がいる:グリーンパイソンによくある寄生虫です。購入店に虫がいることを言って仕入れ時期や寄生虫チェックはいつしたか聞いて病院に良き獣医に聞いたことを伝え、虫がいた排泄物をジップロックなどに入れて、生体と共にいきましょう。海外でこの寄生虫が人間に寄生し脳内で成長していたという事例があります。
健康診断の頻度と方法
一般的には病気の疑いがある場合を除き、定期健診などの必要性はないと考えられております。
健康診断でチェックする項目
同上
他蛇でもありますが、眼がへこんでいる場合、湿度不足か脱皮の皮が目に残っている可能性があります。次の脱皮の時に目の皮が剥がれているかしっかり観察しましょう。
グリーンパイソンの飼育における注意点
多頭飼育
グリーンパイソンは同種に対して社会的な行動を示す種類でもあります。つまり、同じケージに入れていても喧嘩が起こりにくいという事ですが、多頭飼育の場合、給餌方法に難があると言われています。その為過去には日本でもグリーンパイソンはひとつのケージに複数匹入れて管理していましたが、現在では1匹づつ飼育されています。海外においても、給餌のさい、喧嘩にならないように別々であげないといけない事から、多頭飼育者は減っているようです。また、個体差が激しく、同サイズではないとより困難だと言われています。
危険な習性や行動
ハンドリングは好ましくありません。蛇は臆病とよく言われますが、違います。嫌だから攻撃してきます。他の爬虫類や小動物においても臆病な子は攻撃してきません。逃げます。
グリーンパイソンをハンドリングしたがる人がなぜか多いようですが、少なくとも、大きくなるまではやめた方がいいです。大きくなれば、穏やかな性格になることはよく言われていますが、ヤングまでは非常にストレスに弱く、木に登らなくなって死んだなどよく聞きます。これらは、YouTubeを見て真似をして若いグリーンパイソンを頑張って触ろうとして死んだのを販売店が悪いと言い問題になった事が多数あり、販売店などは強く、ハンドリングはできないと言うようになりました。その影響で昨今はハンドリングが容易にできる、ボールパイソンやコーンスネークなどに初心者の人気が集まっています。
グリーンパイソンの攻撃性
本来鳥類の捕食に適した体に進化しています。その為、歯が地表で活動する蛇と比べて鋭く発達しています。これは噛みついた鳥類の羽を貫通させて噛むことに特化しています。
人間に対しては多くの場合「威嚇攻撃」を行います。これは噛みつく意思はなく。口を開けたまま突撃してくるだけです。ですが歯が鋭い為深いケガを負うことになります。
それに対して捕食しようとして噛みついてくる場合は、がぶりと手に噛みついて、手に巻き付いてきます。こうなれば離すまで待つしかありません。その歯が深くまで食い込んでいる場合は動脈まで達して血が噴き出る可能性があります。出血の勢いがすごい場合は、すぐに病院に行くことをお勧めします。
爬虫類飼育経験者向け内容(グリーンパイソンの攻撃性)
首を縮めてる、攻撃の予備動作がわかりやすい為、逃げようとしているのか、噛んで来ようとしているのか見極めは簡単です。あからさまに警戒しているのか落ち着いているのかわかりやすい種類でもあります。他蛇に噛まれたことがある人は、今危険か、慣れてきたか、穏やかになったか、見極めるのは容易だと思われます。ただ、爬虫類に対してハンドリングすることは良くなく、特にグリーンパイソンはヤングまではハンドリングに対してのストレスが強いと言われています。蛇である為、1年に1度以上(冬季に多い)は歯が生え変わります。牙ではない小さな歯は特に換装しやすく、人間に攻撃したときに人間の手に歯だけ残る場合があります。痛みが続くときは、その小さな歯が食い込んだままの可能性があります。
安全性を確保するための対策
逃げない為の対策は十分必要です。生体になったグリーンパイソンは自らの筋力でオブジェクトを破壊することができます。もちろんそのような可能性は低いですが、DIYで自作したケージの場合、容易に破壊できてしまう可能性がある為、骨格を入れて丈夫なつくりにしましょう。
ケージのロックの仕組み
市販のケージの場合、元々ついているロックの機能で十分です、鍵をかけてもグリーンパイソンは丁寧に入口をあけるわけではないの関係ありません。ただし、開きのロックはちゃんとかかっているか、ケージをあけた場合はしっかりチェックしましょう。
取り扱いについての注意事項
ハンドリングを行うときは部屋の外に逃げないように戸締りは最低限行うべきです。
グリーンパイソンの飼育のためのアドバイス
グリーンパイソンとの適切な接触方法
飼育に必要な時間と手間
毎日の水替えが好ましいですが、最低でも2日に1回は水替えを行いましょう。乾燥防止用の水入れを用意している場合はそれも一緒に交換しましょう。また、かわいいからと言ってハンドリングを行うことはNGです。グリーンパイソンは特にハンドリングでのストレスを受けます。
飼育に必要な費用
天井型のヒーターの電気代が常にかかります。サーモスタットを使用して不要なときは自動で切れる仕組みを作りましょう。餌はマウスのリタイアを週1で給餌した場合、300円毎週かかる事になります。
グリーンパイソンの種類と品種
グリーンパイソンの種類と分類
学術名 Morelia viridis で知られるグリーンパイソンは、ニシキヘビ科のMorelia属に属しています。この属には、他にもカーペットパイソンなど、いくつかの大型ヘビが含まれていますが、グリーンパイソンは独特の外見と生態で独自の存在感を放っています。変異遺伝子より産地による色や柄の違いがあります。
代表的なグリーンパイソンの品種と産地
品種(変異遺伝子)
ハイイエロー(High Yellow)
ハイイエローは、黄色い斑点や地肌が特に鮮やかなグリーンパイソンの品種です。これらの個体は、黄色の部分が多く、緑色が少ないことが特徴です。
アクアマリン
アクアマリンは、緑色と青色が混ざった鮮やかな色彩を持つグリーンパイソンの品種です。この品種は、スカイブルーコンドロと似ていますが、より緑色が強いことが特徴です。
キャリコ(Calico)
キャリコは、体全体に白い斑点が多く、まだら模様のような外見を持つグリーンパイソンの品種です。これらの個体は、他の品種と比較して白い部分が大きく、個体差も大きいことが特徴です。
レッドネオン(Red Neon)
レッドネオンは、幼体の時期に赤みがかった色彩を持つグリーンパイソンの品種です。成長するにつれて緑色に変化しますが、赤みが残ることもあります。レッドビアクとは異なります。
産地
いずれもインドネシア原産(アルーやビアクなど)が多いですがオーストラリアにもいます。日本で出回る個体の多くは現在ではビアクが主でその次にアルーです。これらは他国の輸出規制により変動しました。
アルー産
アルー産は、インドネシアのアルー諸島原産のグリーンパイソンです。この地域型は、濃い緑色の体と鮮やかな黄色い斑点が特徴で、成長すると青みがかった緑色になります。
ビアク産
ビアク産は、インドネシアのビアク島原産で、明るい緑色の体に白い斑点が特徴です。この地域型は、他の地域型に比べてやや大型で、体が太くて頑丈です。
レッドビアク(品種&原産)
ビアクの中でも生まれた時に赤色だった個体はレッドビアクと呼ばれます。すぐに黄色に変色しますが、他のビアクとは異なり、成長に伴う変色で緑になる際に、黄色が多く体に残ります。また緑への変化のスピードは他の品種、産地と比べて遅いと言われています。
ソロモン産
ソロモン産は、ソロモン諸島原産で、緑色の体に大きな白い斑点が特徴です。この地域型は、他の地域型に比べて鱗の数が少なく、独特の外見を持っています。
ケープヨーク産
オーストラリアのケープヨーク半島原産のグリーンパイソンで、緑色の体に小さな黄色い斑点が特徴す。ケープヨーク産は、オーストラリア原産の唯一のグリーンパイソンであり、他のインドネシア産地域型とは異なる独自の特徴を持っています。
グリーンパイソンとの生活を楽しむ方法
グリーンパイソンとの遊び方
爬虫類である為、ハンドリングで触れ合うことは推奨されませんが、美しい種類の個体である為、見ているだけでも最高です。
グリーンパイソンは成長に伴いからの色が徐々に緑になって行く為、期間を決めて定期的に写真を撮っていけばどんな風に色が変わっていくか観察できてわかりやすいですね!
グリーンパイソンとのコミュニケーション方法
耳はないので声は届きませんが、声による振動で届きます。蛇は人間とは違い耳の穴はありませんが、しっかり耳は存在します。体が触れている部分の振動が内耳に伝わり音を判断します。
毎日おはようと声をかけるだけで、グリーンパイソンはあなたに心を許していつかハンドリングができる時が来るかもしれません。
ちなみに大きくなればなるほど狂暴性は薄れると言われますが、個体差は大きくあると思われます。
ハンドリング時の注意点
グリーンパイソンはハンドリングは推奨しないといいましたが、脱皮不全でハンドリングしなければいけない状況は来ます。そのときは腕まで保護できる安全手袋を着用しケージから出してあげればいいです。生体にもよりますが、一定時間手袋状態でハンドリングすると、まったく噛まなくなる時間が来ます。その時は素手で触ったりします。手に鼠のにおいがついていたら容赦なく噛んでくるので気をつましょう。
まとめ
グリーンパイソンの飼育は、「インテリア」だと思え、なんていう人がいますが、まさにそうです。生きているインテリア。美しくそしてかっこいい。でも触るのはNG。あまり生き物に対していい言い方だとは思いませんが、それほどハンドリングは良くないってことです。あなたの生活を静かに見守るグリーンパイソンを飼育してみてはいかがでしょうか?
ここまで読んでいただきありがとうございました。当サイトでは、観覧者様のペットの飼育方法の投稿や、ご自身のペットの写真投稿をお待ちしております。
自然界での生態
ギャラリー



更新履歴
R6年3/26 飼育の裏技を追加 タイトルを2024年版に変更