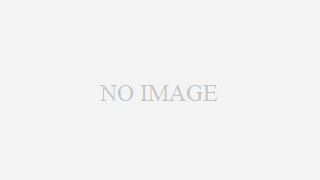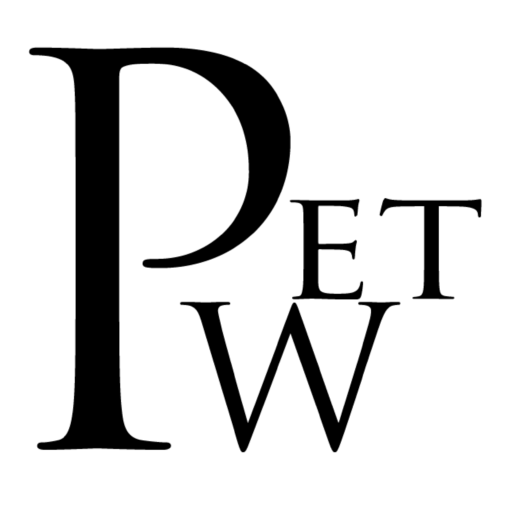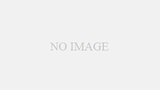はじめに
昨今、「ニドウイルスが流行している」とSNS等で話題に上ることがあります。しかし実は、人類がCOVID-19で大きな混乱に陥る以前から、アメリカではすでにボールパイソンにおけるニドウイルス感染が問題視されていました。このため当初、「人間のコロナウイルスは爬虫類にも感染するのではないか」との誤解が生じた時期もあります。後に、それらのウイルスは同じ「ニドウイルス目」に属するが、「コロナウイルス」ではなく、トバニウイルス科サーペントウイルス亜科に分類される別のウイルス種であることが明らかになりました。台湾においても、ほぼ同時期に感染例が確認されておりアメリカでは公的機関が2014年に検知しています。
本稿では、この「ニドウイルス」および「キャリア」という重要な概念について、最新の研究結果を踏まえた正確な情報提供を目的とします。とりわけ注目すべきは、「発症後に症状が消失してもウイルスを保持し続ける可能性が高い」という近年の知見です。
爬虫類店に行った後、飼育個体が死んだという報告も見受けられましたが、感染後すぐに死ぬと直結させることは困難であり、必ず症状がでます。
本投稿の編集者は、分子生物学やそれらに関連する学問の専攻者ではない為、ウイルスに関する感染方法、特性、または考察は論文からの抜粋としています。
おすすめ動画
以下の動画でボールパイソンのニドウイルスに関する対処方法などが説明されています。そちらの情報を優先することをお勧めします。
記事要点
本稿で取り上げるニドウイルス(Nidovirus)は、過度に恐れるべき病原体ではありません。もちろん、感染していない個体を選好することは飼育者として自然な判断であり、本来であれば感染していない個体を購入することが好ましいです。
ニドウイルスは、いわゆる潜伏感染性を有するウイルスに分類され、宿主の免疫が健全であれば臨床症状を示さないことが多く報告されています(絶対ではない)。これはヒトのヘルペスウイルス属(Herpesviridae)における潜伏感染・再活性化の現象と類似しており、ストレスや免疫抑制などの外的要因によって病態が顕在化するケースが中心です。
また、本ウイルスは完全なウイルスクリアランスが困難なタイプに分類される点も重要です。こうした性質は哺乳類・鳥類・爬虫類を問わず多くの動物種に共通して認められており、ニドウイルスも爬虫類における持続感染性ウイルスの一例に過ぎません。
特に爬虫類においては、キャリア状態で生涯を過ごすウイルスが数多く存在しており、代表的なものにはアデノウイルス、ヘルペスウイルス、アレナウイルス、レオウイルスなどが含まれます。ニドウイルスもその一群に位置づけられるものであり、過剰な忌避よりも適切な理解と管理が求められます。
各論文では免疫の低下による発症、免疫低下なしでの発症、合併症としての発症が疑われており、確定されていない情報が多くあります。
ニドウイルスとは?
ニドウイルス(Nidovirales)は、2014年に初めて爬虫類(ボールパイソン)での感染が確認された新興のRNAウイルス群に属します。ここで注意すべきは、「ニドウイルス」が【個別のウイルス名ではなく、ウイルス分類上の“目”(Order)】であるという点です。コロナウイルス(SARS-CoV-2)もこの分類に含まれます。
ボールパイソンで確認されたウイルスは、確かにコロナウイルスと同じ「ニドウイルス目」に分類されますが、「コロナウイルス科」ではなく「トバニウイルス科サーペントウイルス亜科」に属します。したがって、「ボールパイソンがコロナウイルスに感染した」という表現は不正確であり、分類上はまったく別系統のウイルスです。
※一部で『ボールパイソンニドウイルス(BPNV)』と言われているとされていますが、国際上の分類では公式にBPNVは登録されていません。(2025年6月)
ウイルスの固有名はあるのか?
COVID-19のように、ヒトウイルスには明確な病名やウイルス名が付けられていますが、爬虫類に感染するニドウイルスについては正式な種名が定まっていないケースが多く、便宜的に「ボールパイソン・ニドウイルス」や「グリーンツリーパイソン・ニドウイルス」などと呼ばれています。これは、ウイルスが複数種の爬虫類にまたがって感染する可能性があり、宿主特異性が完全に限定されていないためです。また、国際的なウイルス分類機関(ウイルスの命名、分類(属、科、目など)を国際的に標準化するための唯一の公式機関)ICTV(International Committee on Taxonomy of Viruses)には2025年6月現在ボールパイソンニドウイルス(BPNV)は登録されていません。それらのウイルスは現在ではまとめてサーペントウイルスとされています。
感染する種と検出頻度
最も報告例が多いのは、以下の2種です:
- 1位 グリーンツリーパイソン(Morelia viridis)
- 2位 ボールパイソン(Python regius)
これは、グリーンツリーパイソンは寄生虫感染の可能性が高く、販売前にほぼ例外なく多くの検査をされる種であるため、検出機会が多いことが一因とされています。ボールパイソンにおいては飼育数が非常に多く、また症状出現時に病院で検査されやすいため、発見される機会が比較的多くなっています。
野生下ではオーストラリアの蛇であるグリーンツリーパイソンとジャングルカーペットパイソンで高い感染率が確認されています。その他地域では1%以下であるという観測があります。ただし、グリーンツリーパイソンなどのニドウイルスとボールパイソンのニドウイルスではウイルスの一致率が75%程度であり、完全に同じウイルスではなく、ボールパイソンのニドウイルスは独自進化をしている可能性が示唆されています。
なお、魚類に感染するニドウイルスも存在しますが、これは別系統であり、本稿の中心である爬虫類の「サーペントウイルス」とは区別されます。
複数の論文において、他種への感染も示唆されていますが、同じウイルスと確定された検査は行われておらず推測の域を出ていません。
感染による症状
感染個体では以下の症状が見られることがあります:
- 口腔粘膜の発赤・腫脹
- 粘液の過剰分泌
- 開口呼吸、喘鳴
- 食欲不振、体重減少
- 重症例では間質性肺炎、敗血症、死亡
感染経路
- 直接接触:同一ケージ飼育、脱皮殻の共有など
- 飛沫感染:咳・呼吸による微細飛沫
- 糞便や粘液などを介した間接感染:用具や飼育者の手指などを媒介に感染
これらは、コロナウイルスの感染様式とも類似しており、環境衛生の管理が極めて重要です。しかし、横隔膜がない種族である為くしゃみなどはボールパイソンはできませんが、『鼻吹き』と言われるトカゲなどでも見られる気道の水分を出す行動は存在します。
主な感染は直接感染及び、糞便などからの間接感染とされています。
また、垂直感染はないと一部で言われていますが、各論文を確認した所、垂直感染に関する記述は一つの文献で確認できたものの、『垂直感染は検証していない』という趣旨でした。
無症状キャリアとウイルスキャリア(持続感染)
無症状キャリアとは?
感染後に発症しない、あるいは一時的に回復した個体が、その後もウイルスを体内に保持したまま他個体へ感染させ得る状態を指します。RT-PCR検査によって症状がない個体からもウイルスが検出される例が多く報告されています。
- 感染後90日以上にわたりウイルスが検出された個体が複数報告されており、短期隔離では不十分な可能性が高いです。
- 最新の研究では、2年以上にわたって断続的に陽性を示す個体や、陽性と陰性を繰り返す個体が50%以上存在することも明らかになっています。
【重要】ウイルスキャリア(持続感染個体)
「ウイルスキャリア」は、症状の有無に関係なく、感染後も長期間ウイルスを保持・排出し続ける個体を指します。無症状キャリアとの違いは、感染期間の持続性と感染力の継続性です。
- 体調の変化や環境ストレスによって、ウイルス量の増減が起こることが確認されています。
- ストレス負荷がないと考えうる状況においても病変が確認されています。
- 現時点では、感染後に完全なウイルス排除(ウイルスクリアランス)が自然に起こる可能性は極めて低いとする研究が主流です。
ボールパイソンにおけるニドウイルス感染での致死率
論文の一部ではボールパイソンのニドウイルスによる致死率は75%を超えています。しかしそれらはすでに感染した個体を採取して経過観察をした結果であり、完全にニドウイルスのみの感染での結果ではなく、マイコプラズマなどの感染により、ニドウイルスが発症し、PCRで検知された可能性があります。その情報源である論文は具体的には、『約2年間で採取した感染個体の内75%が死んだ』という結果です。一般的には獣医の受診、処方箋の投薬により改善傾向がみられる報告が多くあります。
実際の飼育下での感染率
アメリカのブリーダーを対象に行ったニドウイルスの検査において12施設、合わせて約650個体中30%の感染が確認されていますが、キャリアが存在する以上、実際の感染率は不明です。
診断方法
- RT-PCR法:口腔や鼻腔からのスワブ検体によるウイルスRNA検出(確定診断法)
- CT/X線検査:肺炎などの器質的病変の確認(補助的)
RT-PCR法は検知率は100%ではありません。
CT/X線検査は病変の確認で用いられますが、ニドウイルスは必ずしも病変がでるとされてはいません。
発見後の管理と飼育対応
- 最も安全な管理法は「生涯隔離」です。
- 一般的には「最低でも90日の隔離」が推奨されますが、前述の通り90日で安全とは限りません。
- 他個体との接触を一切遮断し、器具や飼育者の手袋なども専用に分けて使用することが推奨されます。
🧪 in vitroでの抗ウイルス薬の評価
2023年に発表された研究では、ボールパイソン、グリーンツリーパイソン、スティムソンパイソンから分離された3種のサーペントウイルスに対して、以下の抗ウイルス薬がin vitroで効果を示しました:
- レムデシビル(Remdesivir)
- リバビリン(Ribavirin)
- NITD-008
これらの薬剤は、ウイルスの複製を阻害し、細胞培養系でのウイルス量を有意に減少させました。ただし、これらの投薬によるウイルスクリアランスは確認されていません。
推奨される備品・準備
✅ 専門獣医師との連携体制(感染時に即相談できる関係構築)
✅ 10% 次亜塩素酸ナトリウム(1:10希釈漂白剤)
✅ 70%以上のエタノール消毒液
✅ 使い捨て手袋、スリッパ、マスク
✅ 個体ごとの記録ノート・デジタル記録アプリ(例:RepFunなど)
重要な留意点
- RT-PCRの陰性は「非感染」ではなく「不検出」であると理解すること。検出感度、採取方法、ウイルス量により結果が左右される。
- 症状がなくても感染源になり得る(無症候キャリア)ことを前提とした対応が基本。
- 治療薬は現在存在しないため、「発症させない」「広げない」管理が最も重要な防御策。
- 日本では一般飼育者も販売店も複数を同じケージに入れていたり接触させることはあまりないと考えられるため、特段気を付けることはないと思います。
まとめ
一度感染した個体では、完全なウイルス除去は期待しにくいとされており、長期の管理と隔離飼育が現実的な対策です。ただし、多くの爬虫類は基本的に隔離飼育です、一つのケージに複数匹を入れることは通常繁殖以外ないことの方が多いです。また、販売店においても繁殖後(接触後)の個体を売ることは極稀であり、販売店から広がるというよりも、そこの店が輸入した個体にウイルスがおり、そのまま顧客に提供となるので、通常販売店が悪いとなることはないと思いますが、ウイルスが出たといわれた販売店はかなりイメージダウンにつながってしまいますね。
今後は新規の個体購入の際には30日と言われる隔離機関は90日が良いとなります。
一部論文ではニドウイルスのみの感染での病変の結果が書かれたものが存在しますが、それは病変を見るためのものであり、キャリアを視点とした文献ではない為参照していません。またそれらは、ニドウイルスのみで病気を発症することを発見したものであり、それらを目的とした論文でした。それらから読み取れるのは、ニドウイルスのみで呼吸器疾患を誘発する証明ですが、病変観察の為、安楽死の処置がとられたため、病変の発見はしているものの、それらによる死亡の確認はされておらず、臨床症状は中等度まで進行していたものの、計画的安楽死である為、自然死での死亡例は一例もなかったことが明記されています。
参考文献
ニドウイルスの感染観測関連
| 年・出典 | 対象動物・検討内容 | 主な知見・結論 |
|---|---|---|
| 2019 (Frontiers in Vet Sci)フォーゲルソンら[米国] | 飼育下の混合ヘビコレクション(ニシキヘビ科中心、ボールパイソン・グリーンツリーパイソン等を含む)を28か月追跡調査 | 感染したヘビでは感染が持続し、ウイルスの完全排除(クリアランス)は観察されなかった。感染陽性のパイソン個体では有意に死亡率が増加し(28か月で75%が死亡)、未感染個体では死亡なし。 |
| 2020 (J Vet Med Sci)ヤンら[台湾] | ボールパイソンの症例報告(呼吸器症状とサーペントウイルス感染の確認) | 患者のボールパイソンでサーペントウイルス感染が確定診断され、全ゲノムが解明された初報告。重度の間質性肺炎を呈し、ウイルス感染が病変原因と推定。治療介入の有無に関わらず感染後の長期生存は困難である可能性が示唆された。 |
| 2021 (Frontiers in Vet Sci)オデアら[豪州] | 爬虫類(ヘビ・トカゲ・カメ)におけるニドウイルス感染の総説および文献レビュー | 無症状感染や長期キャリアの存在を強調。PCR陽性ヘビの約4割は無症候であるという調査結果や、2年以上PCR陽性を維持した無症状パイソンの報告が紹介され、症状消失=ウイルス消失ではないと結論付けている。 |
| 2022 (Viruses, MDPI)マクラフリンら[米国] | 野生ビルマニシキヘビ(フロリダ州外来個体群)を対象にした縦断・横断調査(318検体、うち44個体を複数回検査) | 間欠的なウイルス排出(同個体で陽性⇄陰性を反復)が確認された。再陽性時のウイルス配列が初回と同一であったことから陰性は一時的な不検出に過ぎ、感染は持続していると解釈される。著者らはウイルスの完全クリアランスが起こり得るかは未解明であると指摘。 |
| 2024 (Viruses)パリッシュら[豪州] | 絶滅危惧カメ集団におけるサーペントウイルス持続感染の5年追跡研究(※参考:ヘビに関する知見を含む) | カメでの長期感染例を分析し、他種(ヘビやトカゲ)においても持続性・慢性感染が報告されている点を議論。特にヘビでは感染後にウイルスを完全排除できた明確な例が報告されておらず、感染成立時に持続感染へ移行するリスクが示唆された。(※最新のニドウイルス関連論文である為記事に記載蛇ではなく亀の調査) |