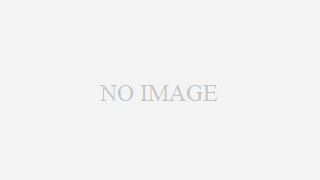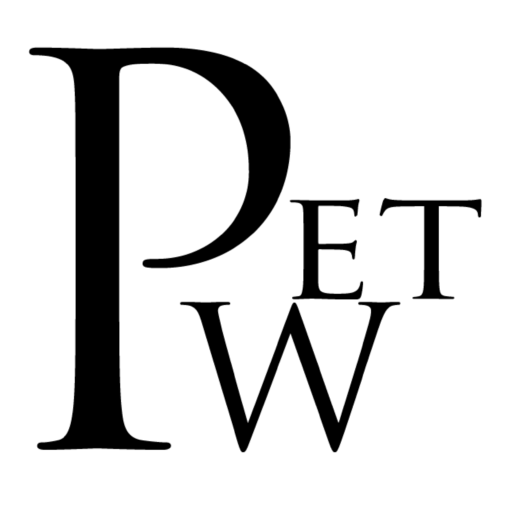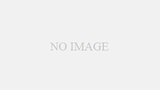【2025年最新版】爬虫類繁殖における必須知識:遺伝の基本法則
はじめに
近年、爬虫類の繁殖はますます盛んになり、それに伴って遺伝学に対する飼育者の理解も深化してきました。かつては、特にボールパイソンを中心に、不正確な遺伝用語の氾濫が国際的にも問題視されていました。しかし、近年では遺伝学の標準的知識に基づいた正しい用語の使用が普及しつつあります。
本稿では、爬虫類繁殖において重要な遺伝概念を、遺伝学的に正確かつわかりやすく整理し、用語の正しい使い方を明確にします。
本稿で使用している用語はアメリカの分子遺伝学の日本語翻訳版を参照しています。また、その参考書の爬虫類に関る部分のみを抜粋しております。
🧬 爬虫類界隈における用語の曖昧性と変遷
かつて、筆者自身もボールパイソンの「モルフ」は単一の遺伝子(アレル)によって規定される形質であり、その遺伝形式は「顕性(優性)」「潜性(劣性)」「共顕性(共優性)」の3つに分類されるという、いわゆる**メンデルの古典遺伝学の延長上にある“遺伝子論”**に基づいて理解していました。
このような見解は、ボールパイソンの遺伝を「単一遺伝子ごとの支配関係」によって説明し、遺伝子の挙動を一義的に捉えるものであり、一時期は他の爬虫類よりも研究的に進んだ分類体系とみなされていました。
しかし近年では、クレステッドゲッコーやレオパードゲッコーと同様に、ボールパイソンにおいても「モルフとは複数の遺伝子変異(多因子変異や連鎖遺伝)の組み合わせにより表現される表現型である」とする、より発展的な見解——**“遺伝子表現論”**に基づいた理解が広まりつつあります。
このパラダイムの転換は、数年前よりMorphMarket(モルフマーケット)を中心に提唱され始め、ボールパイソンの遺伝に関する用語や分類の修正・再定義が行われるきっかけとなりました。
表現型論と遺伝型論
改めて、「表現型」と「遺伝型」という基本的な概念の違いを整理しておきましょう。
冒頭のでも述べた通り、ボールパイソンの繁殖現場では、長らく「遺伝子がどのように伝わるか」に注目する「遺伝型論(genotype-based thinking)」が主流でした。これはメンデル遺伝学を基盤とした考え方であり、親の遺伝子型に基づいて子のモルフを確率的に予測できるという点で、実務上の利便性が非常に高かったためです。多くのモルフがメンデル遺伝の単一遺伝子支配で説明可能であり、表現型の変化が比較的明確だったからです。特に、ピンストライプ、モハベ、パステルといったクラシックモルフは、ヘテロ接合かホモ接合かによって視覚的な違いが判別しやすく、子の見た目から親の遺伝型を逆推定できるという実用的な利点がありました。また、親から子への遺伝において、たとえば「あるモルフが50%の確率で子に遺伝する」といったように、遺伝の法則(メンデルの分離の法則)に則った比率で示せることも、遺伝型論を繁殖戦略の中核に据える大きな要因となっていました。これにより、遺伝の可視性・予測性が高い種として、ボールパイソンは他爬虫類よりも「遺伝を計算する」文化が発展しやすかったのです。
対照的に、現代の分子遺伝学や発生学の分野では、「どのような形質(表現)が実際に現れるか」という「表現型論(phenotype-based thinking)」が主流です。この立場では、アレルの組み合わせそのものだけでなく、それらがどのように相互作用し、さらに環境要因や修飾遺伝子の影響を受けて最終的にどのような表現型になるかを重視します。
なぜ表現型論への移行が進みつつあるのか
しかし近年では、この「遺伝型からすべてが予測できる」という前提に限界があることが明らかになってきました。
その一例が、従来「潜性」と考えられていたモルフの中に、ヘテロ接合でも視覚的変化を示す例が出てきたことです。
たとえば、クラウン(Clown)やデザートゴースト(Desert Ghost)といったモルフは、ホモ接合での表現型が非常に明瞭である一方で、ヘテロ接合であっても体色や模様の整理など、外見に特有の変化が現れることが報告されています。
これは、従来の「完全潜性(recessive)」という定義では説明できず、むしろ「不完全顕性(incomplete dominance)」として再解釈する方が妥当とされています。
つまり、表現型に焦点をあてる表現型論が重要視されるようになってきたのは、「遺伝型だけでは語れない視覚的表現の多様性」が増してきたことが背景にあるのです。
統合での問題点
現在でも多くのボールパイソンのモルフで顕性なのか潜性なのか不完全顕性なのかの議論が続いています。また、表現型論に当てはめてしまうと、ボールパイソンはパターンミューテーションと言われている変異アレルを保持していても、ノーマルの柄(エイリアンヘッド)が少なからず出ている場合があります。つまり、ノーマルが出ている以上、そのモルフは顕性ではなく、不完全顕性で分類されてしまうからです。つまりは不完全顕性という言葉は、過去の共顕性とスーパー体と顕性を大きな括りで囲ってしまい。結果、ほとんどのモルフの説明で、顕性遺伝や共顕性遺伝、コンプレックスだったものが『不完全顕性』と書かれてしまいます。
これらの問題点は爬虫類のみならず人間での医療研究においても問題視されており、表現論に移行した結果、曖昧な状態を放置しその遺伝子の特性を明確化しない。曖昧であるが故にスケーリングできないという問題が発生し、従来の遺伝型論と表現型論の両方の定義が必要であるという論文も見受けられます。
そもそもボールパイソンのモルフは柄を決めてはいない
これらの問題から出てくる課題として、そもそもボールパイソンのモルフという遺伝子または連鎖遺伝は、モルフの柄を決める遺伝子ではない可能性が大きくなります。これらは不完全顕性がほとんどであり、何故か複数のモルフでコンボをしてもその中間的表現が出るからです。つまり私が提言したいのは、ボールパイソンをはじめとする、多くの蛇類のモルフは、とある一つの生体の中にある要素のパラメーターの強弱をつけているに過ぎず、そのパラメーターで表現にかなりの自由度がうまれている。と考えることができます。これを裏付ける情報としてデジタル化が進む以前、一部ブリーダーは現在のノーマルの柄である『エイリアンヘッド』を『フック&リング』と呼んでいたという話があります。またこれらのフックとリングのそれぞれの変化をスケーリングしてモルフを区別していたという話があり。そのアナログ的スケーリングが実際のモルフの核かもしれません。これらは、今回記述している内容とは異なり『モルフ=複数表現型アレル(別名:多面発現的アレル)』という内容になってしまいます。
今回は現在進んでいる議論である。『モルフ=単一の遺伝子』という考えから『モルフ=連鎖遺伝』へのパラダイムシフトという議論の意向に従い解説していきます。
🧬 用語解説
まず、日本遺伝学会によって以下のような用語の見直し・統一が提唱されています:
| 旧呼称(誤用語) | 新呼称(正確な用語) | 英語表記 |
|---|---|---|
| 優性 | 顕性(けんせい) | Dominant |
| 劣性 | 潜性(せんせい) | Recessive |
| 突然変異 | 変異 | Mutation / Genetic Variation |
| 〇〇異常 | 多様性 | Variation |
多様性は環境要因を含むため細かく遺伝を見る今回は利用しません。メンデル関係というより、それらはより大きなダーウィンの進化論に近い考えです。
ミューテーションの分類
遺伝子を細かく見たときはいくつかのミューテーションにタグ付けします。ここでの分類は厳密な分類ではなく、『主にどんな効果を持つモルフなのか』をわかりやすくするために小動物で利用される分類です。遺伝子特定がされていない爬虫類では、一つのモルフが複数のミューテーションに属する可能性があります。
■ パターンミューテーション(模様変異)
定義:
皮膚や鱗の「模様構造(パターン)」に影響を与える遺伝的変異。色ではなく、模様の「配置パターン」に関わる。
解説:爬虫類でいう柄の変化を起こす遺伝子の事を総称してパターンミューテーションと言います。
■ カラーミューテーション(色彩変異)
定義:
体表の色素(メラノフォア、キサントフォア、エリスロフォアなど)に関連する遺伝的変異。
解説:爬虫類でいう体表の色の変化を起こす遺伝子の事を総称してカラーミューテーションと言います。
■ コートミューテーション(構造変異)
定義:
鱗や毛などの体表構造の物理的形態に影響を与える遺伝的変異。
例: スケールレス(レオパ/ボールパイソン)、フラッピー(クレス)など。遺伝的要因が強く疑われる構造変異。
解説:爬虫類では極めて稀な存在です。小動物に存在します。
【重要な改定】接合について
過去には、ボールパイソンを含む多くの爬虫類の遺伝において、「ホモ接合」と「ヘテロ接合」の用語が混同され、大きな誤用がなされてきました。
バナナを元にした交配例:
- パターン1 父親:スーパーバナナ(B/B)
- パターン2 母親:バナナ(B/b)
- パターン3 子供:バナナ(B/b)
- パターン4 子供:スーパーバナナ(B/B)
上記のような遺伝のパターンにおいて、かつてはこれらの変異遺伝子の状態を「ヘテロ/ホモ接合された共優性遺伝子」として説明する媒体が多く見られました。
しかし、遺伝子学に基づいて正確に表現するならば、
- パターン1と4は『変異アレルBを2つ持つホモ接合体(B/B)であり、不完全顕性の表現型として“スーパーバナナ”を示す遺伝型』
- パターン2と3は『変異アレルBと野生型アレルbを1つずつ持つヘテロ接合体(B/b)であり、不完全顕性の表現型として“バナナ”を示す遺伝型』
とされます。
「共優性(共顕性)」という用語は、本来異なるアレルが両方とも等しく完全に表現型として現れる場合(たとえば、牛の赤毛と白毛の両方がまだら模様として現れるようなケース)に用いられるものです。一方、本例のように表現型が2つのアレルの中間的性質を示す場合には、正確には「不完全顕性」と表現するのが適切です。
また、「変異アレル」および「野生型アレル」といった用語の明確な使い分けは、遺伝型の理解において非常に重要です。というのも、「ホモ接合」「ヘテロ接合」といった言葉のみを用いた場合、遺伝の基礎概念が曖昧な読者にとって、変異アレルの“相手”となる遺伝子の存在を意識できないことが少なくありません。つまり、過去の説明だとノーマルには遺伝子が存在しないと間違った事を思い込む人が一定数存在するのです。
実際には、すべてのアレルは対となる遺伝子座上のもう一方のアレルとセットで存在しており、変異アレルがある以上、必ずその“相手”となるアレルが存在しています。この対立するアレルの関係性を明示するためにも、「変異アレル」「野生型アレル」という用語を積極的に用いることが、誤解の回避と正確な遺伝理解の促進において極めて有効だと考えられています。これらは染色体に関する基礎知識を飛ばして遺伝法則を学ぶことによる弊害です。
■ ホモ接合(Homozygous)
定義:
同じアレルを父母両方から受け継いだ状態。
解説:これらのホモ接合という言葉は対立遺伝子について使用する用語です。
例:上記バナナを元にした交配例のパターン1と4が変異アレルBのホモ接合と言えます。ノーマル(b.b)であれば野生型アレルbのホモ接合といえます。
■ ヘテロ接合(Heterozygous)
定義:
異なるアレルを父母から受け継いだ状態。
解説:これらのヘテロ接合という言葉は対立遺伝子について使用する用語です。
例: 上記バナナを元にした交配例のパターン2と3は変異アレルBのヘテロ接合と言えます。
■ 対立遺伝子(アレル)
定義:
同じ遺伝子座(染色体上の位置)に存在し得る異なる遺伝子のバリエーション。
例: アルビノとノーマルは、同じ座にある異なるアレル。
■ 野生型アレル
定義:
その種族のほとんどが所有している遺伝子を野生型アレルと言う。
別解釈:『レガシー遺伝子』『レガシー個体』『オリジナル』
例: ボールパイソンでのワイルドタイプ『エイリアンヘッド』。
■ 変異型アレル
定義:
変異型アレルとは、野生型アレルが突然変異により変化した結果、新たな表現型を示すようになった遺伝子を指します。過去の呼称で言うところの『変異遺伝子』です。
【重要な改定】ドミナンス関係(優劣関係)について
🔄 従来のモルフ表現とその問題点
かつては以下のような単純化された用語が使用されていました:
- 顕性遺伝子:「1つのアレルでも遺伝すれば必ず表現型として現れる」
- 潜性遺伝子:「ヘテロ接合では表現されず、ホモ接合でのみ表現型が現れる」
- 共顕性遺伝子:「ヘテロ接合でも両アレルの性質が共に表現され、ホモ接合ではより強くなる」
これらの説明は遺伝子そのものに対する性質を“固定的”にラベリングする傾向があり、形質を生み出す背後の複雑なアレル間相互作用を過度に単純化してきました。
✅ 現在の正確な理解:表現型重視の視点へ
遺伝型に着目して「モルフ=遺伝子」という認識で扱う「遺伝型論」は、世代間の遺伝予測には現在でも有用ですが、今後は実際にどのような表現型が出るか(表現型論)を重視するようになります。つまに極端にいうと、何が遺伝したかではなく、遺伝した結果どうなったのか。です。その為、以前はどのように遺伝するという観点でしたが、今後は、表現として出る、出ないで遺伝子を説明するのが重要な観点です。
置き換え後の定義:
- 共顕性(Codominance):2つのアレルの性質が並列してそのまま表現型に現れる。
- 顕性(完全顕性)(Dominant):対立アレルの片方の性質だけが表現され、もう一方の影響は見られない。
- 潜性(完全潜性)(Recessive):対立アレルのうち、ヘテロ接合では表現されず、ホモ接合でのみ表現型として現れる。
- 不完全顕性(Incomplete Dominance):2つのアレルが中間的な表現型を形成する。
現在もどれになるのか議論中
現在もそれぞれのモルフに対して、不完全顕性や顕性なのかは議論がされている最中です。ここには大きな問題が発生しており、先も記述した通り、そのモルフがどのような遺伝子なのか明確に判明していない為です。
■ 顕性(完全顕性)(Dominant)
定義:
異なる2つのアレルを持つヘテロ接合体において、片方のアレル(顕性アレル)の表現型のみが現れる遺伝形式。顕性は完全顕性の略
■ 潜性(完全潜性)(Recessive)
定義:
異なる2つのアレルを持つヘテロ接合体において、その表現型が現れないアレル。潜性アレルによる表現型は両方のアレルが同一の潜性アレルのホモ接合のときのみ発現する。潜性は完全潜性の略。
■ 共顕性(Codominance)
定義:
異なる2つのアレルが存在していても、両方の性質が完全にかつ独立して表現型に現れる遺伝形式。
例:
モルモットやハムスターで見られる「白+茶」のぶち模様など。赤白の両色がまだらに現れる毛色もその一例。
補足:
かつてボールパイソンのほとんどのモルフは「共優性(共顕性)」とされていましたが、現在ではそれらは不完全顕性として分類され直されています。
■ 不完全顕性(Incomplete Dominance)
定義:
異なる2つのアレルを持つヘテロ接合体において、2つのアレルの影響が中間的に統合されて発現する遺伝形式。
表現型は、どちらか一方の完全な支配ではなく、「中間的」または「混合的」な特徴を持つ。
例:
赤い花と白い花を交配してできたピンクの花。
また、ボールパイソンにおける「スーパーフォーム(ホモ接合)」と「通常モルフ(ヘテロ接合)」で色調や模様が段階的に変化するものも、この形式に該当します。
補足:
パターンミューテーション、カラーミューテーション、コートミューテーションなど、表現型変化をもたらす多くのモルフは、不完全顕性の性質を持つとされます。
■ エピスタシス
定義:
エピスタシス遺伝子(上位遺伝子)は他アレルに影響を及ぼす。
別解釈:エピスタシスが成立した時、他表現は消失または異なる表現を行う。旧呼称のコンプレックスではありません。特定の遺伝子が他のセットのアレルに対して強烈に影響を与えるときにその特定遺伝子はエピスタシスであると言えます。例えばボールパイソンのエンチはパイボールの白化を抑える効果を持つと言われており、他モルフに対しても特殊な効果を示すモルフであることから、エピスタシスの可能性があります。一部ではエイリアン柄自体の配列をエンチは司ると言われています。
■ スーパーフォーム(スーパー体)
定義:
同一の変異アレルをホモ接合した際に、通常のヘテロ接合体とは異なる、特有の表現型を示す状態。
例:
スーパーパステル(Pastel/Pastel)
スーパーモハベ(Mojave/Mojave)=リューシスティック
補足:
スーパーフォームとは、同一の変異アレルがホモ接合となった際に、ヘテロ接合体よりも顕著または明確に異なる表現型を示す個体を指します。これは遺伝形式そのものではなく、ホモ接合体に特有の視覚的区分です。スーパーフォームを持つモルフは一般に不完全顕性と関連しますが、必ずしも全てのスーパーフォームが不完全顕性とは限りません。
■コンプレックス
定義:
複数のアレルが互いに類似の表現型を示し、それらが同一遺伝子座に位置しており、アレル同士が相互作用する遺伝子群を『コンプレックス』と呼ぶ。
解説:これらコンプレックスは対立遺伝と言われていましたが、正確な遺伝学の用語に当てはめると対立遺伝という言葉は単にアレルを意味する為不適切です。その為現在の正式言い方にすると『複対立遺伝』ですが、そのままコンプレックスや、BELなど、コンプレックスグループの名前で呼ばれます。
モルフという概念の統合
ボールパイソンにおいては先に言った通り『モルフ=遺伝子』とされていましたが、現在は適正語への統合の動きにより、『モルフは単一の遺伝子変異だけでなく、連鎖遺伝(同一染色体上の近接遺伝子群)や多因子の影響を受けて形成される』という考えが広まりつつあります。つまりは、モルフは単一の遺伝子ではなく、染色体上の複数の近所の遺伝子の集合体であり、言い換えれば、複数の遺伝子で一つのモルフを形成しているという、本来の解釈へとかわりました。
■ 連鎖遺伝(Linked Inheritance)
定義:
同じ染色体上に物理的に近接して存在する複数の遺伝子が、減数分裂時に一緒に遺伝しやすくなる現象。
■ 複数表現型アレル(別名:多面発現的アレル)
定義:
1つの遺伝子ではあるが、二つ以上の表現型に影響を与える。
補足:連鎖遺伝は直接表現に影響を与える遺伝子(一次変化)を複数保持しており遺伝するときに同時にそれらの連鎖遺伝子群が同時に遺伝すること。複数表現型アレルは一つの遺伝で、一つの性質に影響を及ぼし、その性質の変化で2次的に複数の表現に影響を与えること。
例: ボールパイソンのバナナ遺伝子においては生体の酵素の活性化を図り、2次的に、体表と目の色の変化を同時に起こすとされている。またその他にも、セックスリンクや巨大化、黒点パラドックスを二次的に起こすとされている。
■単一遺伝(モノジェニック遺伝)(monogeneric)
定義:
単一の遺伝子座(または遺伝子)の変異が、特定の表現型に直接的な影響を及ぼす遺伝形式。明瞭な形質差を示す傾向があり、メンデルの法則に基づいた遺伝が観察されやすい。
解説:
モノジェニック遺伝は、一つの主要な遺伝子の変異が表現型に大きく関与するため、遺伝のパターンが比較的単純で、予測性に優れます。
■多因子遺伝(ポリジェニック遺伝)(Polygenic)
定義:
複数の遺伝子が協調的に影響し、1つの表現型を決定する形式。連続変量(連続的な個体差)を示す。
解説:爬虫類のみならず多くの生物で利用されているがメンデル的遺伝概念において容易に整理できるボールパイソン(モノジェネリック)では利用されていない。つまり、どのモルフが表現にどのような影響を及ぼすのか大まかに明確化されているボールパイソンでは各モルフの表現に関わる主要な遺伝子が比較的特定されているため、一般に多因子遺伝の用語は避けられ、代わりに明確な遺伝子組み合わせを示す『コンボ』という用語が広く使われています。対してクレスやレオパなど、かなりの数の変異遺伝子が合わさった結果生まれる個体のモルフはポリジェネリックと表記され、多因子遺伝とされる。
発展:多くのボールパイソンでは命名に親から継承されたと思われる遺伝子名を組み合わせるが、一部、特定の遺伝子と特定の遺伝子の組み合わせに特殊な名前を付ける場合がある。しかし、それはコンボ名と言わるもので、そのコンボを分解(子に継承)すると、親から継承された遺伝子を再分配できる。対してポリジェネリックは親から受け継いだ遺伝子を子供に同様に分配できない。再現性が困難です。なぜなら、複数の観測できない遺伝子も影響して出来上がった表現だからです。
■ 多因子性遺伝(Multifactorial Inheritance)
定義:
複数の遺伝子+環境因子が共同で形質を決定する遺伝形式。
補足:
ヒトの疾患領域での重要用語ですが、爬虫類ではあまり使われません。環境因子の観測は遺伝子という特定部位の観測において、再現性が確保しづらいため、繁殖モルフの計画設計には不向きとされます。しかし、この用語は今後重要になる可能性があります。特にボールパイソンのパステルなどの遺伝子は人為的に与えるエサを変えることでカラーが変わる可能性があるからである。ポリジェネリック同様、子の表現が再現性のない表現になります。言い換えるなら子供に遺伝させた場合、その子供は親とは違う遺伝子名を持つ遺伝子を持つこととなります。
■ 表現型(Phenotype)
定義:
遺伝型と環境の相互作用により実際に現れる性質・外観。
補足:ボールパイソンの単純な遺伝においては環境要因は明確な観測がされておりません。
■ 遺伝型(Genotype)
定義:
個体が持つ遺伝情報の構成。表現型と異なり、外見に現れない情報を含む。
■ 致死遺伝子(Lethal Gene)
定義:
特定のアレルのホモ接合で、胚の発生や生存に致命的な影響を与える遺伝子。
例: Super Spiderなど。ヘテロ接合では表現可能でも、ホモ接合では死亡や奇形を招く。
■ 複対立遺伝子(複アレル)〈コンプレックスグループ〉
定義:
1つの遺伝子座(locus)に、3つ以上の異なるアレル(対立遺伝子)が存在する状態。
ただし、1個体が持てるのは通常2つまで(父方と母方から1つずつ)です。多くの遺伝子は複対立遺伝子であるとされる。
例: TSK Axanthic, VPI Axanthic などはいずれもアザン(黒白)傾向を持つが、互いに非互換であり、これらは同じ遺伝子座に入る可能性を傾向から示唆されるが、それぞれ別名のヘテロが接合しても表現としては現れない。別名の同遺伝子と言われているものがこの複対立アレルに該当するが、爬虫類分野においてほとんどの場合、別名の同遺伝子は単に同じ遺伝子である可能性が非常に高い。
例2:ボールパイソンにおけるコンプレックスが複対立遺伝子である。一つの遺伝子座に入りうるグループをコンプレックスグループと呼んでいる。BELやYBグループ(スーパーストライプコンプレックスグループ)など。ただし、複対立遺伝子は単にコンプレックスのみを示すだけではなく本来であれば大きなくくりである。
■ 環境要因における遺伝子発現の影響
定義:
環境要因により遺伝子による表現を変える。
補足:環境要因により遺伝子が変化するわけではなく、一つの遺伝子が特定の環境下において二次的に異なる表現をだすことである。例えば以下例でしめす、体の部位の温度により現れる毛の色が変わるなどが該当する。
例:シャム猫やヒマラヤン種のウサギなどは、末梢の温度が低い部位に色素沈着が起こる“温度感受性アレル”を持っており、このような表現型は環境因子による遺伝子発現の調節例として知られています。本来は全身の色を変える変異アレルを保持し表現として出た場合、ラップ状態、すなわち全身同じ色であることが予測されるが、耳や尻尾などの特定の末端部位においてラップ状態を否定し他部位とは異なる色の毛になる。また一部胴体のラップ部位の毛を刈り取り冷やすことで、末端部位と同じ色の毛が現れる。これらの場合、産まれたときは全身同じ色であるが(親の体温の恩恵を強く受ける影響)成長と共に毛の色が変化していく。つまりその変異アレルは温度により酵素の活性、不活性が起こり毛の色を変える遺伝子と言える。
■ 量的変動および連続的変動
定義:
複数の遺伝子と環境要因が相互作用し、表現型が連続的・段階的に変化する現象。
例:パターンAの個体には、毎週餌を与える。パターンBには毎月餌を与える。これらのパターンA、BではAはBより背が伸びたなどの変化が現れる。しかし、必ずしもパターンAで管理した場合背が伸びるとは言い切れず、パターンBの管理でも必ずAより背が伸びないとは言い切れない。つまりこれらは、餌の頻度という環境要因(外的要因)だけではなく、複数の遺伝子座の遺伝子の効果も強く影響している考えられる。
■ ハイブリッド(雑種)
定義:
異なる種や亜種間で交配された個体。多くは染色体数が異なり、生殖的隔離や表現の不安定性を伴う。
例: カーペットパイソン × ボールパイソンなど。
分子遺伝学を理解すれば新たなモルフを創作できるのか
実際に私が読んでいる分子遺伝学の書籍でも、研究により人為的に遺伝子配列を変える例は存在するがそれらは我々一般人が容易にできるものではない。対して、その書籍内でもある遺伝子組み合わせを考え交配または繁殖させることで、人為的に求めた表現型の個体を作ることはできる。以下は現在爬虫類界で行われている新たなモルフのつくり方を紹介します。
■ モルフ 形態的変異型(morphological variant)
定義:
同一種内で、遺伝的な理由により外見的特徴(色・模様・構造など)が異なる個体群
■ モルフ形成 仮説1 人為的連鎖遺伝形成
定義:
連鎖遺伝を人為的に創作する。特定の遺伝子と特定の遺伝子を組み合わせ、連鎖遺伝の形成を人為的に計算して行い、子供にそれらが連鎖遺伝をした場合その連鎖遺伝は新たなモルフと言える。
補足:連鎖遺伝の形成は同一染色体上で行われる。ボールパイソンを例にとると、ボールパイソンは対となる性染色体が合計2本、対となる常染色体が合計34本存在し、それらは両親から受け継いだものである為、性染色体は1本+1本=2本。常染色体は17本+17本=34本となる。連鎖遺伝の形成を行う場合は常染色体の内の1本の中に複数の遺伝子を入れると、連鎖遺伝の形成がされることがある。
結論:連鎖遺伝の人為的形成は極めて困難。極端な話ではあるが、100個のモルフを持った一つの親個体を創作し、それにノーマルの個体を複数交配し、産まれてきた子供の保持しているモルフの傾向を見ると、同じモルフの組み合わせを持った子供が極端に複数産まれているはずである。それらは、親個体の創作で一つの連鎖遺伝の形成に成功し新たなモルフを作れたといえる。ただこれらの方法は現実的ではない。
■ モルフ形成 仮説2 突然変異
定義:
古来から行われてきた一般的なモルフ形成の方法の一つ。ワイルド個体の中から他とは異なる特徴を見抜きその個体を交配し増やし生まれた子供同士または、そのワイルドの親と交配し、異なる特徴のみを顕著に表す様に人為的にインブリードを繰り返す。その結果残った特徴的な表現は新たなモルフと固定することができる。
補足:ワイルド個体やファーミング個体から、変異遺伝子探しをしているだけです。
重要:変異遺伝子を見つけインブリードを行い変異遺伝子だけを残す。それらをボールパイソンのワイルドタイプと言われる200種類以上いる野生柄に非該当だった場合、新たに発見された遺伝子と言える。同時にワイルドタイプにその新たな遺伝子も加わることになる。
爬虫類の遺伝を理解する:遺伝予測の基本と活用方法
爬虫類の繁殖を計画する上で、親個体が持つ遺伝子を把握し、子世代の遺伝子型や表現型を予測することは非常に重要です。この記事では、遺伝予測の基本的な方法と、その実践的な活用方法をわかりやすく解説します。
基本的な遺伝予測の考え方
遺伝予測では、各親が持つ遺伝子型を表にし、子の遺伝子型を確認します。
例として、オスが遺伝子型「Aa」、メスが遺伝子型「Bb」を持つ場合を考えてみましょう。
| メス B | メス b | |
|---|---|---|
| オス A | AB | Ab |
| オス a | aB | ab |
この表は、オス・メスが持つそれぞれの遺伝子型を交配させた時に、子に伝わる可能性のある遺伝子の組み合わせを示しています。
各親は遺伝子の片方(Aかa、Bかbのいずれか)を子に伝えますが、どちらを渡すかは基本的にランダムで確率で言うと50%です。
具体例による遺伝予測の説明
ここで、AとBそれぞれがどのようなタイプの遺伝子であるかを具体的に定義して考えます。
例1:顕性の場合(A, Bが同一の顕性変異アレル)
顕性アレルとは、遺伝子型がヘテロ(Aとaなど)でも表現型が変異として現れる遺伝様式です。
- 子の遺伝子型:AB, Ab, aBの場合
→ 親と同じ変異した見た目(顕性表現)が現れます(確率 3/4)。 - 子の遺伝子型:abの場合
→ ノーマルの見た目になります(確率 1/4)。
例2:潜性の場合(A, Bが同一の潜性変異アレル)
潜性アレルとは、ホモ(同じ潜性遺伝子が揃う)でないと表現型が現れない遺伝様式です。両親はヘテロ(見た目ノーマルだが潜性アレルを持つ)である場合を考えます。
- 子の遺伝子型:ABの場合(潜性遺伝子が揃う)
→ 変異の表現型が現れます(確率 1/4)。 - 子の遺伝子型:Ab, aB, abの場合(潜性遺伝子が揃わない)
→ 見た目はノーマルです(確率 3/4)。
例3:不完全顕性の場合(A, Bが同一の不完全顕性変異アレル)
不完全顕性アレルとは、ヘテロの状態で中間型や混合型の表現が現れる遺伝様式です。
- 子の遺伝子型:AB(ホモ接合)
→ 両親よりも強い表現型が現れます。 - 子の遺伝子型:Ab, aB(ヘテロ接合)
→ 親と同じような中間的な表現型が現れます。 - 子の遺伝子型:ab(ノーマル)
→ ノーマルの表現型です。
「ポッシブル」の意味
爬虫類界では、遺伝子型が不確実な状態を「ポッシブル」と呼びます。これは特に顕性遺伝の際に使われます。
- 顕性の変異アレルを1つ(ヘテロ接合)持つ場合
→ 見た目は変異ですが、次世代には必ずその変異アレルを伝えるとは限らず、ノーマルの子が生まれる可能性があります。 - 顕性同一の変異アレルを2つ(ホモ接合)持つ場合
→ 見た目はヘテロ接合と変わりませんが、次世代には必ず変異遺伝子が伝わります。この遺伝子型が不明確なため「ポッシブル〇〇」と表現します。
複数遺伝子を含む場合の遺伝予測
上記の表は単一の対立遺伝子座について示したものです。
複数の遺伝子座を考える場合、より複雑な「組み合わせ」の考え方を使います。
例えば、オスが遺伝子「A, B」を持ち、メスが「C」を持つ場合の子の遺伝子型の組み合わせは以下のようになります。
- ABC
- ABc
- AbC
- Abc
- aBC
- aBc
- abC
- abc
このように、遺伝する可能性のある遺伝子の組み合わせは、各遺伝子座が2種類(例:A/a、B/b、C/c)存在する場合、「2のX乗(Xは遺伝子座数)」で求められます。この例では3つの遺伝子座のため、8種類の組み合わせがあります。
さいごに
本稿では、爬虫類繁殖における遺伝の基本法則を、現代の遺伝学に即して体系的かつ詳細に解説しました。特にボールパイソンのモルフに見られるような複雑な遺伝様式や誤用されがちな用語の再定義、そして遺伝型論から表現型論への転換などは、今後の繁殖戦略や品種改良において極めて重要な視点となります。
また、爬虫類の遺伝は単なる確率計算ではなく、生物の進化的背景や環境との相互作用を含んだ、非常に奥深い領域です。今後さらに分子レベルでの解析が進めば、これまで「モルフ」と呼ばれてきた表現型の多くも、より精密な定義と予測が可能になるでしょう。
繁殖者として、そして生物を扱う責任ある飼育者として、誤解に基づいた知識に頼るのではなく、正確な遺伝的理解のもとで次世代に命をつなぐことが求められます。本記事が、その第一歩となれば幸いです。